人時生産性とは?生産性を下げる5つの原因と4つの対策

人時生産性に課題を感じていませんか?「人員配置にいつも頭を悩ませている……」「頑張って働いているはずなのに、なかなか成果に繋がらない……」といった悩みを抱える方は少なくありません。
日々の業務に追われるなかで、「今の働き方が本当に会社の成長に貢献できているのか」と不安になる方は少なくありません。限られた時間と人員で最大限の成果を出すため、多くの企業が模索しているのが「人時生産性」の向上です。
この記事では、人時生産性とは何か、その阻害要因と、成果を高めるための具体的な改善ポイントについてわかりやすく解説します。
人時生産性とは

人時生産性とは、従業員1人が1時間あたりにどれだけの成果を生み出したかを示す指標です。この「成果」は業種によって異なり、売上高・生産量・顧客対応件数などが該当します。
重要なのは、「投下した労働時間に対してどれだけの価値を生み出しているか」を客観的に把握することです。人時生産性を意識することで、非効率な業務プロセスや無駄な労働時間が可視化され、改善の糸口が見つかります。
人時生産性のポイント
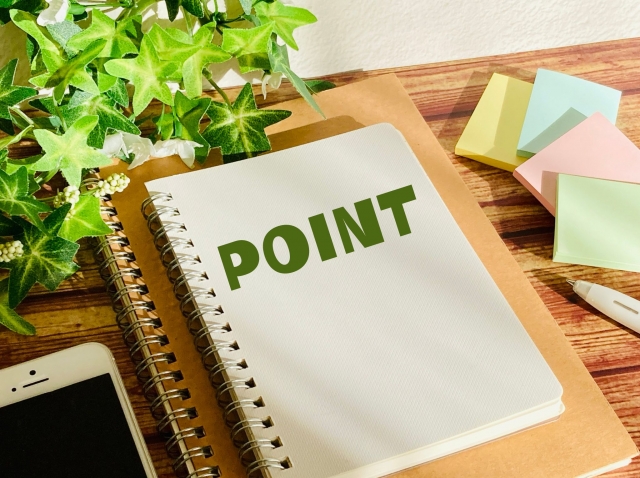
以下の4点に分けて詳しく解説します。
- 人時生産性の計算式
- 人時生産性の具体例
- 労働生産性との違い
- 人時売上高との違い
1. 人時生産性の計算式
人時生産性を算出する基本式は次の通りです:
人時生産性 = 成果(粗利益など) ÷ 総労働時間
この式により、投入した労働時間からどれだけの成果を得られたかを算出できます。数値が高いほど、1人あたりの1時間の成果が大きい=生産性が高いと判断されます。
なお、労働時間には実際の業務時間を用います。従業員1人あたりの労働時間や特定業務に費やした時間など、目的に応じて定義を明確にしておくことが重要です。
2. 人時生産性の具体例
例1:小売業の場合
あるアパレルショップで、1日の売上が50万円、総労働時間が50時間だった場合:
人時生産性 = 50万円 ÷ 50時間 = 1万円/時間
これは、従業員1人あたり1時間で1万円の売上を上げている状態です。
翌日、売上が60万円・労働時間が60時間でも同様に1万円/時間となり、売上は増えたものの生産性は維持されたと評価されます。
例2:製造業の場合
ある工場で、1週間の生産量が1,000個、総労働時間が200時間だった場合:
人時生産性 = 1,000個 ÷ 200時間 = 5個/時間
新しい設備を導入し、同じ労働時間で1,200個生産できれば:
人時生産性 = 1,200個 ÷ 200時間 = 6個/時間
と、1時間あたりの成果が向上し、生産効率が改善されたことがわかります。
3. 労働生産性との違い
「労働生産性」と「人時生産性」は混同されやすい用語ですが、指標としての視点が異なります。
- 労働生産性:産出量 ÷ 労働投入量(企業全体の効率性を評価)
- 人時生産性:成果 ÷ 総労働時間(1人1時間あたりの効率を評価)
例えるなら、労働生産性はチーム全体の総合力、人時生産性は個々の選手の得点力を示すイメージです。目的に応じて使い分けることが重要です。
4. 人時売上高との違い
人時売上高は「売上高 ÷ 総労働時間」で算出される指標で、従業員1人が1時間あたりにどれだけの売上を上げたかを示す指標です。主に小売業や飲食業など売上に直結する業種で用いられます。
例えば、上記「人時生産性の具体例」の例2が該当します。
一方、人時生産性は成果の定義がより広く、売上高だけでなく、生産量・対応件数・成約件数なども含まれます。そのため、製造や管理部門などでも活用しやすい指標です。
このように、人時売上高が人時生産性に含まれる関係にあります。また、人時売上高は「売上」という単一の成果に着目するのに対し、人時生産性はコストや粗利益を考慮し、より実態に即した効率性を測れるという違いがあります。
人時生産性向上を阻む5つの原因

人時生産性を向上させるには、阻害要因を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。主な要因として、以下の5つが挙げられます。
- 手作業によるロス
- 非効率な業務プロセス
- スキル・教育不足
- コミュニケーション不足
- モチベーションの低下
中でも特によく見られるのが、自動化されていない手作業の存在です。たとえば、Excelで管理できる情報を手計算で集計していたり、本来であればロボットやAIに任せられる作業を人が行っている場合は、非効率な業務プロセスとなっている可能性があります。
また、従業員のスキル不足や教育体制の不備も、生産性低下の大きな要因です。必要なスキルを持たない状態で業務にあたると、作業時間の増加やミスの発生につながり、最終的には意欲やエンゲージメントの低下を引き起こします。集中力や積極性が失われることで、生産性の低下を招きかねません。
人時生産性を向上させる4つのポイント

人時生産性を効果的に高めるには、多角的なアプローチが求められます。ここでは、特に重要な4つのポイントを紹介します。
1. 適切な人員配置
人員配置は、生産性向上において重要な要素です。スキルや経験、適性を考慮せずに行われた配置は、従業員の能力を十分に発揮できない要因になります。各人の強みを把握し、最適な役割を与えることで、個々のパフォーマンスを最大限に引き出しましょう。
あわせて、多能工化の推進も有効です。特定の業務に人材が集中しないようにし、柔軟な人員配置が可能な体制を構築することが求められます。
2. 従業員の配置見直し
市場の変化や事業戦略の転換に応じて、既存の人員配置を適宜見直すことも重要です。現在の配置が最適とは限らず、業務負荷が偏っている場合は、思い切った再配置が効果を発揮します。
そのためには、部署ごとの業務内容と必要スキルを可視化し、人員の過不足を客観的に分析することが必要です。異動やローテーションも活用し、組織全体のバランスを整えることが、生産性向上につながります。
3. モチベーションの向上
モチベーションは従業員の生産性に直結します。意欲の低い状態では、期待される成果を上げることが難しくなり、人時生産性は低下します。
適切な評価制度やインセンティブ制度を整備し、努力が正当に報われる環境を作ることが重要です。さらに、キャリアパスの明示や、成長機会の提供などを通じて、従業員が長期的に意欲を持てる環境を整えましょう。
4. ITシステムの活用
ITツールの活用も、生産性向上には欠かせません。定型業務やルーチン作業は可能な限り自動化し、従業員がより付加価値の高い業務に集中できるようにしましょう。
たとえば、コミュニケーションツールやプロジェクト管理ツールを導入することで、情報共有が円滑になり、チーム全体の生産性向上に寄与します。
導入するITシステムは、企業ごとの課題に応じて選定することが大切です。まずは、自社の業務課題を明確にし、それに適したシステムを検討しましょう。
まとめ

人時生産性は、限られた人的リソースの中でどれだけ効率的に成果を上げられるかを示す、経営において非常に重要な指標です。手作業や非効率な業務フロー、スキルや教育の不足、コミュニケーションの課題、さらにはモチベーションの低下といった要因が積み重なることで、知らず知らずのうちに生産性は大きく損なわれてしまいます。これらの原因を放置していては、従業員のパフォーマンスを最大限に引き出すことはできません。
人時生産性を高めるためには、一人ひとりの適性を活かした人員配置や業務の可視化、多能工化による柔軟な対応力の強化など、現場に即した取り組みが求められます。さらに、モチベーションを引き出す制度設計や、ITシステムを活用した業務の効率化も欠かせません。属人的な業務を減らし、再現性と安定性のある業務プロセスを構築することが、持続的な成長に繋がります。
まずは、自社の業務にどのような非効率が潜んでいるのかを洗い出し、小さな業務改善から取り組んでみましょう。原因と向き合い、適切な対策を講じることが、人時生産性の改善、そして企業全体の生産性向上への第一歩となります。
