5Sを導入する効果とは?進め方までわかりやすく解説
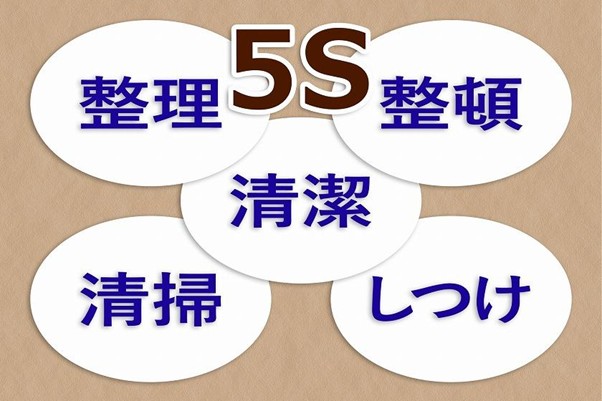
5Sとは、職場環境を整え、効率的かつ快適に作業を進めるための整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)の5つの要素を指します。
この考え方を取り入れることで、作業の無駄を省き、ストレスを軽減し、生産性を向上させることができます。もし「仕事で無駄な動作が多い気がする」「仕事場が散らかって集中できない」と感じたことがあるなら、5Sの実践が解決の鍵になるかもしれません。
今回は、5Sの基本やメリット・デメリット、導入後の効果について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
5Sとは

5Sは、職場環境を改善・維持するためのスローガンです。整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)の5つの要素で構成され、それぞれの頭文字を取って「5S」と呼ばれています。もともと製造業やサービス業で活用されてきましたが、近年はTOYOTAが採用したことで注目を集めています。
以下では、それぞれの要素について詳しく解説します。
整理
必要なものと不要なものを区別し、不要なものを取り除くことを指します。家庭で行う部屋の掃除や片付けと同じ考え方ですが、5Sでは以下のような対象が含まれます:
- 商品在庫
- 道具
- 書類
- データ
- 情報
これらを整理することでスペースが確保され、必要なものを素早く見つけられるようになります。例えば、パソコンのデスクトップに大量のファイルがある状態を整理するだけでも、業務効率が向上します。整理によって無駄が減り、生産性の向上やコスト削減が期待できる重要なステップです。
整頓
必要なものを使いやすい場所に配置することを指します。整頓には、物の置き場所だけでなく、置き方や表示なども含まれます。これにより、必要なものを探す時間を削減し、作業効率を高めることが可能です。
例えば、文房具を引き出しに整理して置く場合、頻繁に使うものを手前に配置するといった工夫が考えられます。整頓は作業効率の向上だけでなく、職場全体の生産性向上にも大きく貢献します。
清掃
職場や道具を掃除し、綺麗な状態を保つことを指します。定期的な清掃により、機械や道具の故障を防ぎ、安全性の向上が期待できます。清掃を効率的に行うためには、目標を設定し、ルールや手順を明確にすることが重要です。
清潔
整理・整頓・清掃を徹底し、綺麗な状態を維持することを指します。一度整った環境をそのまま保つには、ルールやガイドラインの設定が効果的です。常に快適な職場環境を維持することで、事故を防ぎ、安全性を高めることができます。
躾(しつけ)
ルールやガイドラインを習慣化し、継続的に実行できるようにすることを指します。人間は慣れると手を抜きがちですが、職場全体で意識を共有し、責任を持って行動することで5Sを根付かせることができます。
個人の習慣化だけでなく、組織全体での意識共有が重要です。ルールを業務の一部として取り入れることで、職場環境の改善を継続できます。
5Sの目的

5Sの目的は、作業環境を改善し、効率を向上させることです。整理整頓ができていない職場では、無駄が多く、時間やエネルギーを浪費してしまいます。これは、散らかった部屋で必要なものを探すのに時間がかかる状況と同じです。
こうした無駄をなくすために、5Sを実践します。整理・整頓・清掃・清潔・躾を徹底することで、作業効率の向上だけでなく、生産性の向上やリードタイムの短縮といった課題解決も可能になります。
整理された机で作業がはかどるように、5Sを取り入れた環境は快適さを生み、仕事や生活の質を向上させます。これにより、モチベーションもさらに高まるでしょう。
5Sのメリット・デメリット
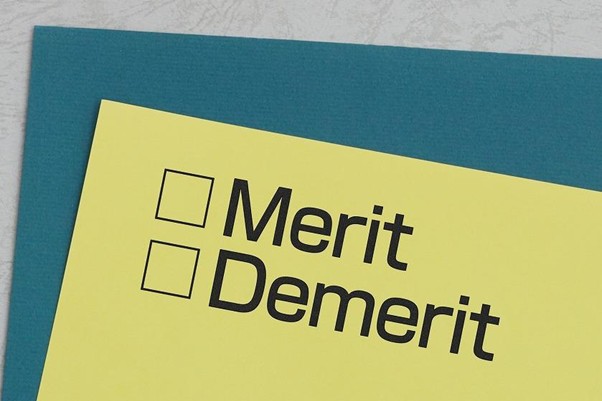
5Sには多くのメリットがある一方で、実施に際してはデメリットも存在します。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
5Sのメリット
5Sを導入することで、以下のようなメリットが得られます
- 無駄の削減
- 作業効率の向上
- 生産性の向上
- 安全性の向上
- 社員の意識改善
整理と整頓により無駄を削減し、作業が効率化することで、生産性や安全性も向上します。例えば、大塚商会の調査では、ビジネスパーソンが必要なものを探す時間は年間約150時間にのぼるとされています。この時間を削減できれば、大きな業務改善が期待できます。
また、整理整頓がされていない環境では、「割れ窓効果」により社員の士気が低下し、生産性に悪影響を及ぼします。5Sを徹底することで、職場環境を整え、社員の意識を改善する効果も得られます。
5Sのデメリット
一方、5Sを導入する際には以下のデメリットも考慮する必要があります。
- 導入と維持にコストがかかる
- すぐに効果が現れにくい
5Sを実践するためには時間や労力が必要です。また、既存のやり方を変えることで、社員から不満が出る場合もあります。特に多忙な職場では、5Sの維持に割く時間を確保することが課題となることがあります。
さらに、5Sの効果は徐々に現れるため、モチベーションを維持しながら取り組むことが重要です。全員が意識を高め、継続的に実践できる体制を整えることが、成功の鍵となります。
5Sの効果

5Sを徹底することで、作業効率や安全性が劇的に向上します。業種によって効果の出方は異なるものの、以下のような共通の成果が期待できます。
- QCD(品質・コスト・納期)の向上
- 保全業務との連携強化
- IoT化の促進
- 伝達ミスの防止
5SはTOYOTAが発祥の考え方としても知られ、特に製造業で大きな効果を発揮します。TOYOTAでは、単に不要なものを取り除くだけではなく、誰が見ても必要なものの所在が一目で分かり、簡単に取り出せる状態を目指しています。これにより、物を取り出す際に他の物を動かすといった無駄を排除しています。
5Sは中途半端に実施すると効果が得られにくいため、徹底的に取り組むことが重要です。
5Sの進め方

5Sを導入する際は、以下の手順に沿って進めましょう。
- 5Sに取り組む目的を明確化する
まず、5Sに取り組む目的を明確にします。この際、「不良品発生率を○%以下にする」といった具体的な数値目標を設定すると、効果が分かりやすくなります。 - 明確化した目的を社内で共有する
次に、設定した目的を社内で共有します。社員全員が目的を理解し、共通の意識を持つことが重要です。 - 業務プロセスを可視化し、5Sのイメージを具体化する
業務プロセスを可視化し、5Sを導入した際の理想的な状態をイメージします。これにより、ゴールが明確になり、社員が取り組みやすくなります。 - 計画に沿った実施
最後に、計画に沿って5Sを実施します。一度で完璧にするのは難しいため、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回しながら、最適な形を追求してください。
5Sを成功させる鍵は、全員の協力と継続的な取り組みです。手順に沿って進め、効果的な職場環境を実現しましょう。
まとめ
5Sは、整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)という5つのステップを通じて、職場環境を効率的かつ快適に改善する手法です。
これを徹底することで、無駄を削減し、作業効率や安全性、生産性を大幅に向上させることが可能です。また、職場環境の改善により、社員の意識改革やチーム全体のモチベーション向上にもつながります。一方で、5Sの実施には一定の時間や労力が必要であり、特に初期段階では計画的な取り組みが求められます。
目的を明確化し、社内で共有することで社員全員が同じ方向性を持ち、持続可能な形で進めることが成功の鍵です。5Sをしっかりと取り入れることで、職場全体がより効率的で魅力的な環境となり、企業全体の成長を後押しする基盤を築くことができるでしょう。
