経理業務を効率化するツール|生成AI・OCR活用で月10時間削減

経理の現場では、請求書や領収書の処理、データ入力、仕訳作業などに膨大な時間が費やされています。
「時間に追われて残業が続く」
「入力ミスが心配で確認作業に手間がかかる」
そんな悩みを抱えている経理担当者は少なくありません。
従来の経理業務は紙やPDFからの手作業入力が中心で、正確さとスピードの両立が求められる一方、人的リソースには限界があります。集中力と注意力を要する作業が多いため、負担も大きくなりがちです。
「このままでは業務が回らなくなるのでは?」
「もっと効率的に進める方法はないだろうか?」
そう感じている方に向けて、本記事では 経理業務を効率化するためのツール をご紹介します。ツールを導入するとどのように業務が変わるのか、実際の活用事例もあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
経理業務の効率化とは

経理業務の効率化とは、従来の手作業中心のプロセスを見直し、時間短縮と正確性の向上を同時に実現することを指します。システムやツールを活用して自動化を進め、手作業を最小限に抑える取り組みです。
効率化の対象となる主な業務には、次のようなものがあります。
- 請求書や領収書の処理
- データ入力
- 帳簿作成
これらを自動化することで、経理担当者は単純な入力や確認作業から解放され、財務分析や経営判断のサポートなど、付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。
近年はクラウドサービスやAI技術の進歩により、こうした自動化が現実的なものとなっています。自社に最適なツールを導入できれば、単なる作業時間の短縮だけでなく、業務品質の向上やヒューマンエラーの削減といった効果も期待できるでしょう。
経理業務の効率化が必要な理由

現代の企業経営において、経理業務の効率化は避けて通れない課題です。その背景として特に大きいのが 人材不足 です。限られた人的リソースで増加する業務量に対応しなければならず、多くの企業が頭を抱えています。
成長企業では取引件数の増加に伴い帳票処理も急増しますが、経理担当者を簡単に増員できるわけではありません。売り手市場が続く中、必要なスキルを持つ人材を確保するのは容易ではないのが実情です。
さらに、手作業中心の業務にはスピードの限界があり、月末や決算期には残業や休日出勤が常態化しがちです。人による作業には必ずミスのリスクが伴うため、チェックや修正にも多大な時間がかかり、担当者の負担は一層増大します。
こうした状況を打開する鍵が「効率化」です。
効率化を進めることで、
- 経理部門の働き方改革を実現できる
- 他部門との連携が強化され、業務全体の流れがスムーズになる
- 企業全体の競争力とパフォーマンスが向上する
経理業務の効率化は単なる業務改善にとどまらず、企業全体の成長を支える基盤づくりといえるでしょう。
経理業務の効率化に役立つおすすめツール紹介

経理業務を効率化するためのツールは多岐にわたります。特に取り入れやすいのは以下のサービスです。
| 業務 | おすすめツール |
| 経理業務 | freee、マネーフォワード、弥生会計 |
| データ入力・仕分け作業 | ジールアルAI、Excel(マクロ必須)、AI-OCR、Webスクレイピング、RPA |
クラウド会計ソフトで経理業務全般を効率化
freeeやマネーフォワード、弥生会計といったクラウド会計ソフトは、銀行やクレジットカードと連携して取引データを自動取り込みできます。手入力の負担を大幅に削減できるため、経理業務全般の効率化に適しています。
データ入力や仕分け作業にはAI・OCRツールを活用
ジーニアルAIなどのOCR技術を搭載したツールを使えば、紙やPDFの帳票から文字や数値を自動で認識しデータ化できます。転記作業をはじめとした業務効率が大幅に向上します。
経理業務は多岐にわたるため、単一のツールで全てをカバーするのは難しい場合があります。複数のツールを組み合わせることで、経理業務の大部分を自動化し、効率を向上させることが可能です。
関連記事:エクセルへの転記を自動化する方法|帳票データのAI活用術
生成AI・OCR技術が経理業務をどう変えるのか?【最新動向】

従来のOCRでは読み取り精度に課題がありましたが、生成AIと組み合わせることで手書き文字や複雑な帳票レイアウトも高精度で認識できます。紙媒体の請求書や領収書をスキャンするだけで、必要な情報を自動抽出可能です。
さらに生成AIは、読み取ったデータを理解し、勘定科目への自動仕訳や異常値の検出も行えます。例えば、請求書から商品名や金額を抽出するだけでなく、過去データと照合して妥当性をチェックしたり、類似取引から最適な処理方法を提案したりできます。
これにより、生成AIとOCR技術の組み合わせは、単純作業から判断を伴う業務まで幅広い経理業務の自動化を可能にします。経理担当者は単純作業から解放され、分析や戦略的業務など、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
ジーニアルAIが実現する経理業務の革新
ジーニアルAIは、AIとOCR技術を活用し、帳票データの読み取りとExcelへの自動転記を同時に実現する、業務効率化ツールです。紙・PDF・画像の帳票をOCRで読み取り、必要な情報を抽出してExcelのセルに自動で入力します。
読み取り対象は、テキストデータとテーブルデータです。複数のテーブルをまとめて転記したり、レイアウトを変更したりすることも可能で、転記業務が多い部署ほど大幅な効率化が期待できます。
- テキストクリップ
書類に埋め込まれたテキストがなくても、範囲選択することでAIが文字を読み取り、テキスト化します。1件ずつの書類処理に最適です。 - テーブルクリップ
書類内のテーブル情報をまとめてExcelに転記できます。明細情報を取り込んで数百のセルを一括転記できるので、手作業による入力工数を大幅に削減できます。
さらに、時間のかかる誓約書や契約書の要約・翻訳もサポートします。特定の観点から要約したり、重要度に応じた情報を取捨選択したりできるため、従来の確認作業を大幅に短縮可能です。文字数制限はありますが(要約:40,000字以内、翻訳:49,000字以内)、実務上十分対応できる範囲です。
生成AIによる翻訳機能も搭載しており、英語や中国語など多言語への翻訳が可能です。部分的な翻訳にも対応しているため、海外取引の多い企業にとって強力なサポートとなります。
このように、ジーニアルAIはOCRと生成AIの技術を組み合わせることで、単純なデータ転記から文書の要約・翻訳まで幅広く対応し、経理業務を大幅に効率化します。導入により、作業時間の削減と業務の高度化を同時に実現できるでしょう。
ジーニアルAIの導入効果と活用事例のご紹介
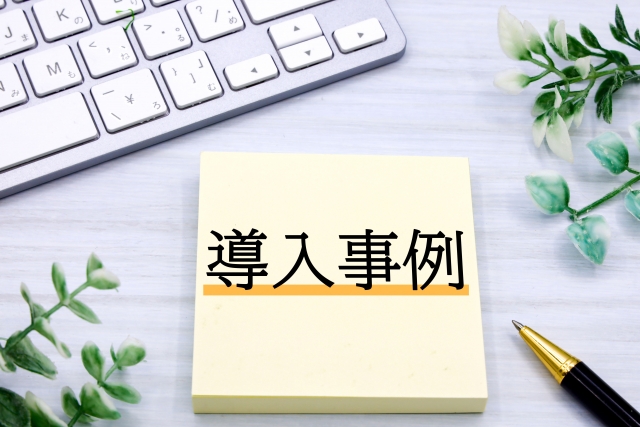
【食品業・経理部門】
課題:
見積書・請求書の手入力に多大な作業を行っており、月初には約30件の請求書処理に2日間を要していました。特に桁数の多い番号や金額の入力ミスが発生しやすく、それに起因するストレスも大きな課題でした。
導入した製品:
この課題を解決するために導入されたのが、Excelアドイン型の自動転記ツール「ジーニアルAI OCR」です。
導入の決め手:
手書き文字にも対応したOCR精度の高さと、書類上のデータをマウスで選択するとそのままExcelに貼り付けられる「クリップ機能」の高い実用性でした。
導入効果:
- 入力ミス(例:「03」と「30」の誤り)が大幅に減少
- 1件あたりの処理時間が15分 → 10分に短縮
- 月初処理の2〜3時間分を削減
- 業務負担とストレスが軽減され、前向きに仕事へ取り組めるように
- 他部署でも「自分たちも使いたい」という声が上がり、現場主導のDXが社内に波及
- 属人化の防止にも効果あり
【卸売/小売業・経理部門】
課題:
取扱商品数の増加に伴って大きな負担が発生。主要仕入先だけで月3,000行以上もある請求データの手作業による突合処理に6日間を要していました。処理の遅延や支払いミス、在庫過多のリスクが顕在化していました。
導入の決め手:
コロナ禍で請求書のデジタル化が進んだことを契機に、管理部門の提案で「ジーニアルAI」をトライアル。作業効率化による時間削減効果を検証でき、Excelベースで操作が簡単である点から導入を決定。
導入効果:
- 主要3社の突合作業が6日間 → 1日未満に短縮(80%以上削減)
- 「不一致データのみを確認する」効率的な業務フローが確立
- 請求金額のミスを即座に発見でき、支払いリスクを回避
- エラーの可視化により、現場の意識と処理スピードも向上
- 毎月5日分の業務時間を創出し、DX推進や付加価値業務に充当
- 「テキストクリップ」「テーブルクリップ」機能で紙の見積書入力も効率化
- 安定したシステムのため、導入後もサポートを必要としない運用が可能
まとめ
経理業務の効率化は、現代の企業にとって不可欠な取り組みです。従来の手作業中心の業務では、増加する業務量に対応しきれず、ヒューマンエラーのリスクも避けられません。しかし、AIやOCRなどの最新技術を活用することで、これらの課題を根本的に解決できます。時間のかかる作業から解放され、経営に必要なコア業務に人材を集中させることが可能になります。
特にジーニアルAIのような高性能ソリューションを導入すれば、帳票処理の自動化により、大幅な時間短縮と品質向上を同時に実現できます。経理業務の効率化は単なるコスト削減ではなく、担当者がより戦略的で付加価値の高い業務に専念できる環境を作る取り組みです。
効率化の第一歩としては、まず従来の業務フローを分析し、自社に最適な自動化・改善の方法を検討することが重要です。企業ごとの業務スタイルに応じた最適化を図ることで、真の業務効率化が実現できます。

