経理の属人化が招く3つのリスク – DXで実現する安心できる経理体制の作り方
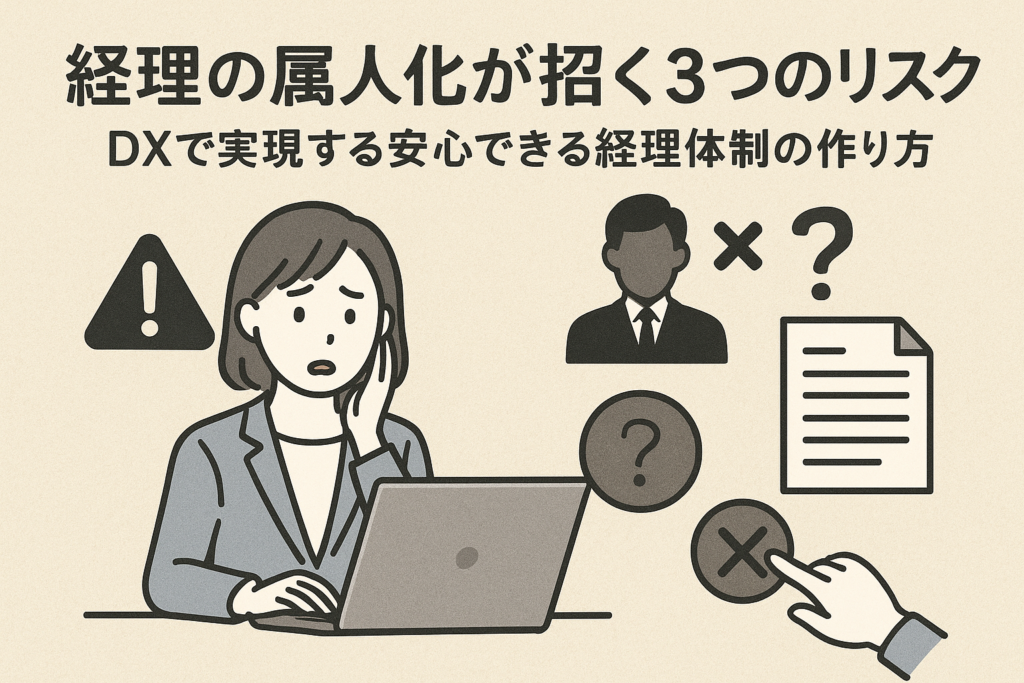
「このファイル、〇〇さんしか触れない」「月次決算が特定メンバーのスケジュール次第」「転職・異動・休職で業務が止まる不安」
そんな状態が当たり前になっていませんか?
経理業務の属人化は、担当者個人の能力や努力の問題ではありません。属人化は「仕組み」の問題です。適切なツールとプロセスがあれば、誰でも業務を遂行できる体制を構築できます。
本記事では、経理業務の属人化がもたらす3つのリスクについて解説しています。その他、「経理DXとは何か」「DXによる属人化解消の具体的な方法」「今日から始められる小さなステップ」についても考察しているので、ぜひ参考にしてください。
なお、2025年11月20日正午から30分のウェビナーを予定しており、本記事の内容に加えて「属人性排除の3つのカギ」や「今日からできる属人性排除の進め方 4ステップ」、事例紹介なども盛り込んでお話しします。

では、経理の現場では具体的にどのような属人化が起きているのでしょうか。
経理業務における属人化の実態
経理業務における属人化とは、特定の担当者にしかできない業務が存在する状態を指します。多くの企業で、このような状況が日常的に発生しています。
現場でよく見られる具体例として、以下のようなケースがあります。
特定のExcelファイルを特定の人しか扱えない状況です。ファイルの構造や数式が複雑で、作成者以外が触ると計算が狂ってしまう不安があります。月次の売上集計表や予実管理表など、重要な帳票ほど属人化しやすい傾向があります。このため、担当者が休暇を取る際も、他のメンバーが業務を引き継げません。
月次決算のスケジュールが特定メンバーの予定に依存するケースもあります。特定の担当者がいないと決算作業が進められないため、その人の予定に合わせて全体のスケジュールを調整せざるを得ません。決算期には、担当者の有給取得を制限せざるを得ない企業も少なくありません。
さらに深刻なのは、転職・異動・休職時に業務が停止する状況です。担当者の退職が決まってから慌てて引き継ぎを始めても、業務の全体像を把握するのに時間がかかります。特に、長年同じ担当者が業務を行っていた場合、その人が持つ暗黙知は膨大です。結果として、業務の継続性が脅かされます。
では、なぜこのような属人化が起こるのでしょうか。主な原因は3つあります。
1. 業務手順の文書化不足
多くの企業では、業務の進め方が担当者の頭の中にしか存在しません。マニュアルがあったとしても、実際の判断基準や例外処理の方法までは記載されていないことがほとんどです。「前期と同じように処理する」という暗黙のルールが、次第に誰も説明できない慣習になっていきます。
2. システム化の遅れ
紙の伝票やExcelでの手作業が中心の業務では、担当者ごとに独自の方法が生まれやすくなります。同じ業務でも、Aさんは手書きの下書きをしてから入力し、Bさんは直接システムに入力するといった違いが生じます。
3. OJT中心の教育体制
先輩から後輩へ口頭で伝えられる知識は、体系的に整理されていないため、受け取る側によって理解度に差が生まれます。「見て覚えろ」という指導では、なぜその処理をするのかという背景が伝わりません。
あなたの会社では、誰が何を担当しているか、全員が把握できていますか?
属人化が企業に与える影響
属人化を放置すると、企業に大きなリスクをもたらします。特に重要なのは、以下の3つです。
1. 業務のブラックボックス化
判断基準が個人の頭の中にあり、他人が追跡できない状態になります。例えば、売掛金の回収判断や引当金の計上基準など、重要な会計判断が担当者の経験則に依存していると、その妥当性を検証することができません。
業務プロセスが可視化されず、改善も困難になります。「なぜこの処理をするのか」が担当者本人にしか分からないため、業務の無駄を発見したり、より効率的な方法を検討したりすることができません。
実際に、ある企業では10年以上続けていた月次処理が、担当者の退職を機に見直したところ、すでに不要になっていた処理が複数見つかったという事例もあります。このブラックボックス化は、組織全体の生産性を低下させます。
2. 内部統制リスク
誤処理や不正を見逃しても発見が遅れる可能性があります。特定の担当者しか業務に関わっていない場合、チェック機能が働きません。相互牽制の原則が機能せず、ミスや不正が長期間放置される恐れがあります。
監査対応にも支障が出ます。監査人から質問を受けた際、担当者以外が答えられないため、監査の効率が低下します。場合によっては、担当者の不在時に監査が進められず、スケジュールに影響が出ることもあります。
内部統制報告制度(J-SOX)への対応が不十分になる可能性もあります。J-SOXとは、金融商品取引法に基づく社内管理体制の報告制度のことです。業務プロセスが文書化されておらず、複数人によるチェックも機能していないと、内部統制の評価において問題が指摘される恐れがあります。
3. 教育・引き継ぎコストの増大
OJTは非効率になりがちなので、新人の育成に時間がかかります。体系的なマニュアルがないため、新人は先輩の作業を見ながら少しずつ覚えていくしかありません。これでは、一人前になるまでに長い時間が必要です。企業によっては、新人が独り立ちするまでに1年以上かかるケースもあります。
また、離職・異動時にノウハウが消失します。担当者が退職すると、その人が持っていた知識やスキルが組織から失われます。後任者は、前任者と同じレベルに達するまでに、同じ道のりを一から歩まなければなりません。特に、ベテラン社員の退職時には、数十年分の経験とノウハウが一度に失われることになります。
業務の継続性が確保できないと、組織全体の生産性が低下します。引き継ぎ期間中は、前任者も後任者も通常業務と並行して対応するため、双方に負担がかかります。この期間、チーム全体の業務効率が大幅に下がることは避けられません。
属人性を放置することは、経理の生産性低下とリスクの温床となります。
経理DXと聞いて、「うちの会社には早い」と感じていませんか?実は、DXは大企業だけのものではありません。
経理DXの定義と重要性
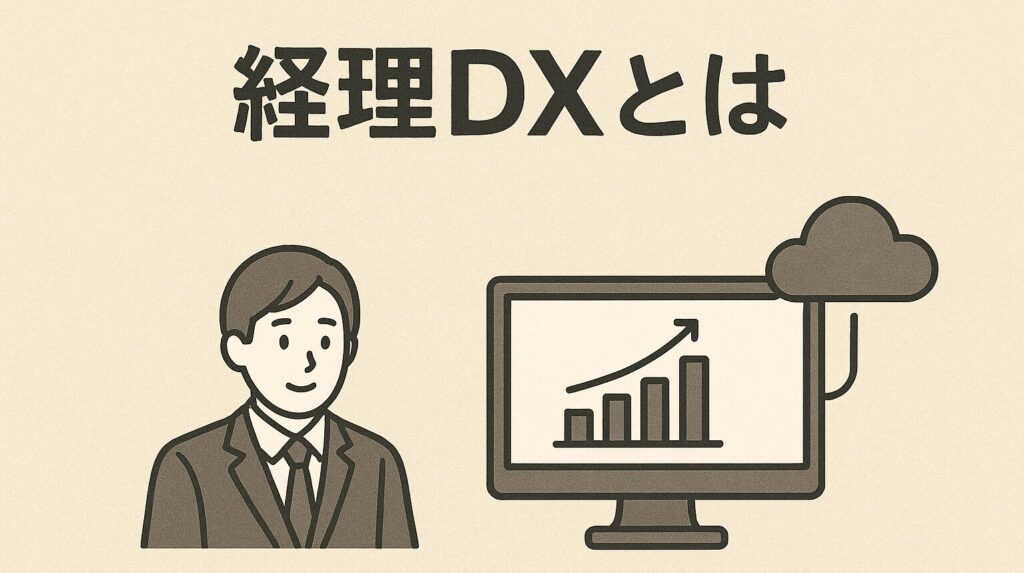
経理DXとは、デジタル技術を活用した経理業務の変革を指します。単なる効率化にとどまらず、生産性の向上だけでなく、新たな価値の創出に貢献します。
経理DXは、以下の3つの段階を経て進化します。
1段階目:デジタイゼーション
紙媒体をデジタル化し、データとして保存・管理する段階です。例えば、紙の請求書をスキャンしてPDF化したり、手書きの伝票を電子データとして記録したりすることが該当します。
この段階では、紙からデジタルへの移行が中心となります。ファイルキャビネットに保管していた書類を、クラウドストレージに保存するだけでも、検索性が向上し、リモートワークにも対応できるようになります。
2段階目:デジタライゼーション
クラウド等を活用し、業務プロセス全体を改革する段階です。クラウド会計ソフトを導入して、複数人が同時にアクセスできるようにしたり、承認フローを電子化したりすることが含まれます。
この段階では、業務の進め方そのものが変わります。紙の稟議書を回覧していた承認プロセスが、システム上で完結するようになります。出張中でもスマートフォンから承認できるため、業務のスピードが大幅に向上します。
3段階目:デジタルトランスフォーメーション
AI等を活用し、業務の抜本的な改革を実現する段階です。AIが請求書のデータを自動で読み取って会計システムに入力したり、異常なデータを検知して担当者に通知したりするなど、人間の判断を補助する仕組みが導入されます。
この段階では、経理担当者の役割が大きく変化します。データ入力作業から解放され、データ分析や経営支援など、より戦略的な業務に時間を使えるようになります。
従来の経理との違いは明確です。
自動化による手作業の削減で、データ入力や照合作業にかかる時間を大幅に短縮できます。月末に数百枚もの請求書を手入力していた作業が、AI-OCRによって数時間で完了するようになります。
データ活用による意思決定の高度化により、リアルタイムに財務状況を把握し、経営判断のスピードが上がります。月次決算を待たずに、今月の売上や経費の状況を把握できるため、迅速な対策が可能になります。
リアルタイムな情報共有によって、チーム内での連携がスムーズになり、属人化の解消にもつながります。誰がどこまで作業を進めたかが一目で分かるため、担当者が不在でも業務が止まりません。
経理DX導入のメリット
経理DXを導入することで、大きく4つのメリットがあります。
1. 業務効率の向上とコスト削減
手作業の削減による時間短縮が実現します。請求書のデータ入力を手作業で行っている企業では、一ヶ月に数百枚もの請求書を処理することも珍しくありません。AI-OCRを導入することで、この作業時間を大幅に削減できます。ある企業では、月間100時間かかっていた入力作業が、20時間に短縮された事例もあります。
ヒューマンエラーの減少も期待できます。人間が手入力する際には、どうしても誤入力が発生します。特に、数字の桁を間違えたり、小数点の位置を誤ったりするミスは、後々大きな問題になります。AI-OCR結果を人間がレビューすることで、このようなミスを防ぐことができます。
人件費や紙媒体費用の削減にもつながります。定型業務が自動化されることで、担当者はより付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。また、紙の伝票や請求書を電子化することで、印刷費や保管スペースのコストも削減できます。紙の請求書を7年間保管するための倉庫費用は、意外と大きな負担です。
2. データの可視化と意思決定の迅速化
リアルタイムな財務状況の把握が可能になります。従来の経理では、月次決算が締まるまで正確な数字が分かりませんでした。多くの企業では、月初から10日程度かけて前月の数字を確定させています。しかし、クラウドシステムとデータ連携を活用すれば、いつでも最新の状況を確認できます。
データに基づいた経営戦略立案ができるようになります。過去のデータを分析することで、売上の傾向や費用の変動を把握し、将来の予測に活用できます。季節変動のパターンや、曜日による売上の違いなど、これまで見逃していた傾向が見えてきます。
経営層への報告業務の効率化も実現します。レポートを手作業で作成する必要がなくなり、システムから必要なデータを抽出してグラフ化することが可能です。経営会議の資料作成に丸一日かかっていた作業が、数時間で完了するようになります。
3. ガバナンスとコンプライアンスの強化
証憑の一元管理による内部統制の強化が図れます。全ての証憑書類を電子データとして保存し、システム上で管理することで、誰がいつどの書類を確認したかが記録されます。この監査証跡により、内部統制の有効性を証明できます。
監査証跡の明確化により、監査対応がスムーズになります。システムに記録されたログを確認することで、取引の流れや承認プロセスを容易に追跡できます。監査人からの質問に対して、すぐにエビデンスを提示できるため、監査時間の短縮にもつながります。
法令遵守(電子帳簿保存法など)への対応も進みます。2024年1月から電子帳簿保存法の要件が見直され、電子取引データの保存が義務化されています。メールで受け取った請求書PDFなども、適切な方法で保存しなければなりません。経理DXを進めることで、このような法改正にも対応しやすくなります。
4. 従業員満足度の向上
定型業務からの解放により、担当者のモチベーションが向上します。単純なデータ入力作業から解放され、データ分析や業務改善など、より創造的な業務に取り組めるようになります。経理担当者が「やりがい」を感じられる仕事が増えることで、離職率の低下も期待できます。
また、より戦略的な業務へのシフトが可能になります。経理担当者は、単なる記帳係ではなく、経営判断を支援するビジネスパートナーとしての役割を担えるようになります。経営層に対して、データに基づいた提案ができるようになることで、経理部門の存在価値が高まります。
ワークライフバランスの改善にもつながります。月次決算時の残業が減り、休暇も取りやすくなります。これは、属人化が解消され、誰でも業務を進められる体制が整うためです。経理担当者が安心して有給休暇を取得できる職場は、人材の定着にも好影響を与えます。
DXで実現する「誰でもできる仕組み」
DXによる属人化解消には、3つのアプローチがあります。
業務の可視化
業務フローの文書化が第一歩です。現在の業務の流れを図式化し、誰がどの作業を担当しているかを明確にします。これにより、業務の全体像が把握できるようになります。フローチャートを作成することで、無駄な工程や、属人化している箇所が一目で分かります。
判断基準の明文化も重要です。「このケースではこう処理する」というルールを文書化することで、担当者によって判断が異なる状況を防げます。例えば、「金額が10万円以上の場合は部長承認」「海外取引の場合は為替レートを〇〇で確認」など、具体的な基準を設定します。
マニュアルのデジタル化により、情報の更新と共有が容易になります。紙のマニュアルは更新が面倒で、最新版がどれか分からなくなりがちです。デジタル化することで、常に最新の情報を参照できます。クラウド上で管理すれば、リモートワーク中でもアクセスできます。
ツールの活用
クラウド会計システムの導入により、複数人が同時にアクセスできる環境を整えます。これにより、特定の担当者のPCでしか作業できないという状況を解消できます。在宅勤務でも、外出先でも、同じシステムにアクセスして業務を進められます。
AI-OCRによる証憑データの自動取り込みで、データ入力作業を削減します。請求書や領収書をスキャンするだけで、必要な情報が自動的に抽出され、会計システムに連携されます。手書きの文字でも認識精度が高く、従来のOCRと比べて大幅に精度が向上しています。
RPA(Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型業務の自動化も効果的です。毎月同じ手順で行う作業をロボットに記憶させることで、人間の作業を減らせます。例えば、複数のシステムからデータをダウンロードして集計する作業など、ルーティンワークに威力を発揮します。
チーム内での情報共有
作業ログの共有により、誰がどこまで作業を進めたかが分かるようになります。これにより、担当者が不在でも他のメンバーが状況を把握し、業務を継続できます。プロジェクト管理ツールやチャットツールを活用することで、リアルタイムに情報を共有できます。
ナレッジベースの構築で、過去の事例やトラブル対応方法を蓄積します。同じ問題が発生した際に、誰でも解決方法を参照できるようになります。「こういうエラーが出たらこう対処する」という情報を、社内Wikiやドキュメント管理システムに記録していきます。
チェックリストの標準化により、作業の抜け漏れを防ぎます。経験の浅い担当者でも、チェックリストに沿って進めれば、必要な作業を完了できます。月次決算のチェックリスト、年次決算のチェックリストなど、業務ごとに標準化されたリストがあれば、誰が担当しても同じ品質を保てます。
今日から始められる属人化解消の小さなステップ
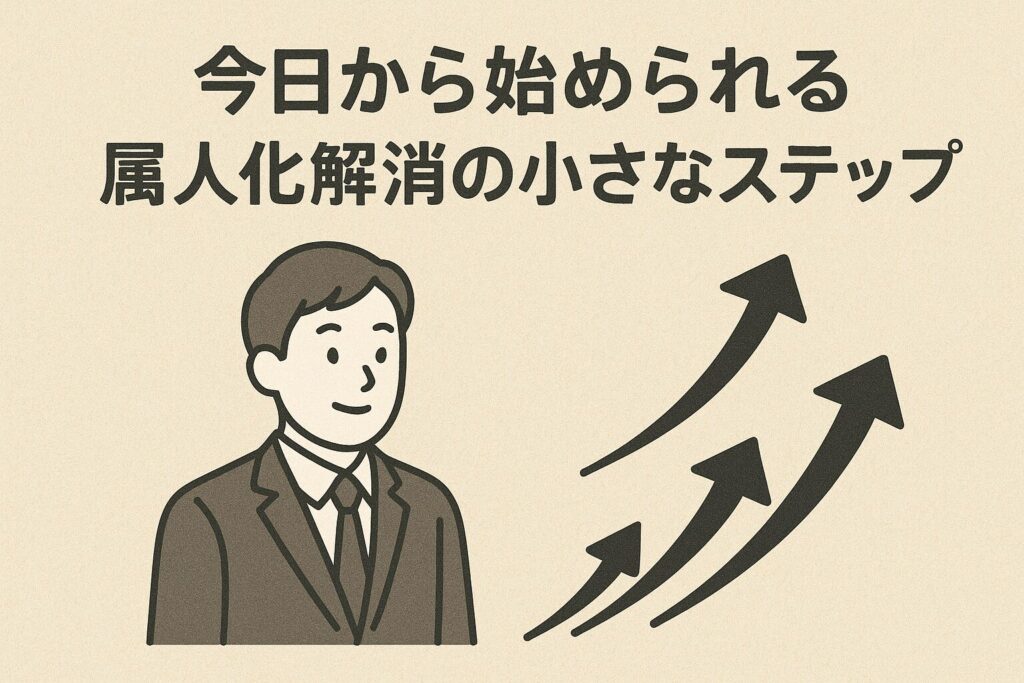
DXの導入と聞くと、大掛かりなプロジェクトを想像するかもしれません。しかし、まず小さなステップから始めることが重要です。
ステップ1:業務の棚卸しをする
最初の一歩として、現在の業務をリストアップし、「誰にしかできない業務」を洗い出すことから始めましょう。チーム全員で業務を書き出し、担当者が1人しかいない業務に印をつけます。この作業だけでも、属人化の実態が見えてきます。
具体的には、Excelやスプレッドシートに以下の項目を記入します。
- 業務名
- 担当者
- 頻度(毎日、毎週、毎月など)
- 所要時間
- 他の人でもできるか(○、△、×)
この表を作成することで、どの業務が属人化しているか、どの業務が時間を取っているかが可視化されます。
ステップ2:優先順位をつける
洗い出した業務の中から、優先的に対処すべきものを選びます。以下の基準で判断すると良いでしょう。
- リスクが高い業務(担当者不在時に業務が止まる)
- 頻度が高い業務(毎日または毎週発生する)
- 時間がかかる業務(月間10時間以上)
すべての業務を一度に改善しようとすると、負担が大きくなります。まずは、影響の大きい業務から着手しましょう。
ステップ3:簡単なマニュアルを作る
完璧なマニュアルを目指す必要はありません。「こういう時はこうする」という判断基準を箇条書きにするだけでも、大きな前進です。
例えば、以下のような簡単な形式で十分です。
【月次売上集計の手順】
- 販売管理システムから月次売上データをCSV出力
- 「売上集計テンプレート.xlsx」を開く
- CSVデータをシートにコピー
- ピボットテーブルを更新(データタブ→すべて更新)
- グラフが自動更新されることを確認
- PDFで保存し、経理フォルダに格納
【注意点】
- 期首の場合は前年データをクリアする
- 返品がある場合は手動で調整する
このようなメモ書き程度のマニュアルでも、次の担当者にとっては貴重な情報です。
ステップ4:チーム内で共有する
作成したマニュアルを、チーム全員がアクセスできる場所に保存します。個人のPCではなく、共有フォルダやクラウドストレージに置くことが重要です。
また、定期的に見直しの機会を設けましょう。業務は変化するため、マニュアルも更新が必要です。四半期に一度、チームミーティングでマニュアルの内容を確認し、修正点があれば更新します。
これらのステップは、特別なツールがなくても今日から始められます。完璧を目指す必要はありません。できるところから、一歩ずつ進めていくことが重要です。
これらのアプローチを実践する上で、特に効果的なのが「作業と証憑の紐づけ」です。ここでは、その具体的な実現方法として、ジーニアルAI OCRの「クリップ機能」をご紹介します。
ジーニアルAI OCRの「クリップ機能」で実現する経理の透明化
ジーニアルAI OCRの「クリップ機能」を使えば、Excelファイルに書類を取り込んでセルと書類箇所を紐づけて表示できるようになります。これにより、チーム内で作業を追跡できるようになるので、一元化に役立ちます。
具体的な効果として、以下が期待できます。
誰が、いつ、どの書類を処理したかが可視化されます。Excelのセルと証憑書類が紐づいているため、このセルのデータはどの書類のどの部分から転記されたのかが一目で分かります。例えば、売上明細のセルをクリックすると、該当する請求書のPDFが開き、転記元の箇所がハイライトされます。
チーム内で作業ログを共有することで経理の透明化を進められます。担当者が入力した内容を、他のメンバーがレビューする際、元の書類を探す手間が省けます。セルをクリックするだけで、該当する書類の箇所が表示されるためです。ファイルキャビネットから紙の書類を探し出す必要も、PDFファイルを開いて該当ページを探す必要もありません。
担当者不在時でも、他のメンバーが業務を引き継げます。作業の履歴と根拠となる書類が全て紐づいているため、引き継ぎ資料を作成する必要がありません。システム上で全ての情報を確認できます。急な休暇や病欠でも、他のメンバーがすぐに状況を把握し、業務を継続できます。
このように、ジーニアルAI OCRは属人化解消の有力なツールとして活用できます。
まとめ
属人化をなくすことは「人を減らす」ことではありません。経理が安心して休める、引き継げる、相談できる体制をつくることです。それを支えるのが、今のDXツールです。
経理DXは、単なる効率化だけでなく、企業の競争力強化に不可欠です。変化を恐れず、一歩踏み出すことが重要です。
未来の経理部門を創造するために、まずは業務の可視化から始めてみませんか?完璧を目指す必要はありません。できるところから、一歩ずつ進めていくことが重要です。
今日からできる小さなステップは、業務のリストアップです。チーム全員で「誰しかできない業務」を洗い出すだけでも、属人化の実態が見えてきます。そこから、優先順位をつけて、一つずつ改善していきましょう。
2025年11月20日正午から30分のウェビナーを予定しています。ウェビナーでは本記事の内容に加えて、「属人性排除の3つのカギ」、「今日からできる属人性排除の進め方 4ステップ」、ジーニアルAI OCRのデモ、事例紹介なども盛り込んでお話しします。

ご興味のある方は、こちらからお申し込みください。
https://corp.genialtech.io/ja/news/genial-seminar-20251120/
